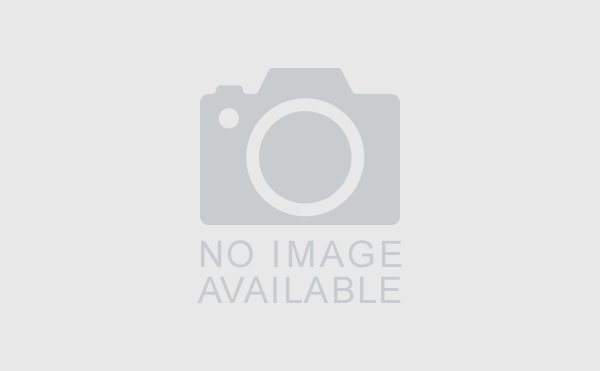食品安全委員会のPFAS評価についての申し入れと回答
食の安全・監視市民委員会では、4月1日、食品安全委員会におけるPFAS評価の過程で文献の差し替えが不適切に行なわれているとの高木基金の指摘を受け、食品安全委員会に文献の差し替え理由や経緯を開示することを求める申し入れ書(質問状)を送りました。4月10日に回答が来ましたが、「評価作業やその前提となる文献収集作業に対する誤解に基づくものである」とする内容で、文献の差し替え理由や経緯は開示されませんでした。納得できる回答でありませんので、改めて説明を求めていきます。
【申し入れ書(質問状)】
2025年4月1日 内閣府食品安全委員会 委員長 山本茂貴 様 食の安全・監視市民委員会 申し入れ書 食品安全委員会におけるPFAS評価の不当性について 環境省は有機フッ素化合物PFAS評価の見直しをおこなっていますが、その際、食品安全委員会が令和6年6月26日、自ら評価としてPFASについて公表した評価結果を重視しています。しかし、高木基金PFASプロジェクトが令和7年3月3日に公表した「検証レポート」よると、貴委員会は、「耐容一日摂取量(TDI)」を導くにあたり、当初PFASのリスク評価に必要とされた論文257報を参照するとしたものの、7割以上を差し替えていたとされています。事前選定で「AA」(最重要文献:リスク評価の根幹として最重要と考えられる文献)とされた165報のうち122報を除外する一方、「C」評価(関連性が低い文献:評価には不要と考えられる文献)を含む201報を追加していたとされています。私たちは、こうした多数の論文を差し替えたことについて、意図的な配慮をおこなった恐れがあると感じています。貴食品安全委員会はそうした差し替えの作業について、その理由や経緯を公表するべきです。4月10日までに公表してください。また公表されない場合は、その理由を当委員会あてに文書で回答するよう申し入れます。 以上 |
【回答】 ※メールでの回答
| 2025年4月10日 申し入れ書「食品安全委員会におけるPFAS評価の不当性について」に対する回答 食の安全・監視市民委員会 御中 申し入れ書の中の「多数の論文を差し替え」や「意図的な配慮をおこなった」といったご指摘は、我々の評価作業やその前提となる文献収集作業に対する誤解に基づくものである、と食品安全委員会としては考えています。この観点から、既に3月19日に一般の方向けに「有機フッ素化合物(PFAS)」評価書に関するQ&A」を公表しております。 ここではより詳細に説明させていただきます。 食品安全委員会は2022年度調査事業として、「化学物質評価研究機構」にPFASについての情報収集と整理を依頼し、2023年3月に報告書を受領しました。同機構は、海外の評価書で引用されている文献及び、学術論文のデータベースから一定の検索条件により抽出した論文の中から、タイトルおよび概要のみに基づいて内容確認を行い、評価に使用できる可能性がある文献を選定しました。さらに、ランク付け(AA等)を行った上で、本文も取り寄せて食品安全委員会に提出しました。これらの選定やランク付けは、専門家を集めた「検討会」の意見を聞いて実施されました。 この「検討会」の委員のうち11人に新たな専門家12人を加える形で食品安全委員会に設置したPFASワーキンググループにおいては、各分野の専門家である専門委員・専門参考人が、すべての論文を手分けして、丁寧に全文読み込みました。また、海外の評価書において指標値を算出する根拠となった文献及びその評価を取りこぼすことのないように、注意深く文献確認を行いました。調査事業では見落とされていた「海外の評価書で指標値の算出に用いられた主要な文献」の多くを、第2回ワーキンググループ会合(2023年5月)において追加補足して議論を開始するなど、ワーキンググループにおいては先行する海外の評価書での議論を十分踏まえた形で評価を行いました。 計9回の会合を重ねて2024年6月にまとめた評価書は、食品を通じて摂取するPFASの健康影響について、数多ある文献からもたらされる知見を統合し、科学的に矛盾のない結論として示されたものであり、その結論に至るうえで必要不可欠な文献を評価書の参照文献として整理しております。 22年度の調査事業でのランク付けは、評価を進めるにあたり、あくまでも初期段階の情報の整理の目的で行なわれたものです。したがって、調査事業でタイトル及び概要だけから「AA」とされ、評価書においては参照文献として記載しなかったものがあるほか、逆に当初のランク付けは低かったものの、全文を読み込んだ結果、評価書の結論に至るうえで重要と判断し、参照文献として記載したものもあります。また、科学的論拠が十分でない部分について、専門家が独自に文献検索を行って補強し、参照文献として追加したケースもあります。 調査事業で「化学物質評価研究機構」が作成したリストでは、欧州食品安全機関(EFSA)や米国環境保護庁(EPA)が指標値を決定する際の根拠として用いた重要な論文が多数抜けておりました。これらを上記のプロセスで追加し、評価に取り入れ参考文献として記載した点にご留意ください。 このような評価の作成プロセスは、汚染物質の評価においては、一般的なものです。評価の過程で関係のある文献をすべて考慮したうえで、評価書の文章は、食品健康影響評価の論旨を明確にする観点から、結論に至る過程で必要な科学的知見を軸にして構成し、参照文献として科学的知見の根拠となる文献を記載します。 したがって、貴団体ご指摘の「事前選定で最重要文献とした論文の一部を除外し、評価の低い文献を含め論文を追加し、多数の論文を差し替えた」との見方は、評価のプロセスを無視したもので適切ではない、と考えます。検討と議論の過程は、公開している議事録でご確認ください。「意図的な配慮」の可能性を示唆する内容はない、と考えております。 食品安全委員会の評価書にご関心を持っていただき「申し入れ」をしていただいたことに感謝申し上げます。今後も「国民の健康保護が最も重要である」という基本的認識のもと、科学的根拠に基づくリスク評価とリスクコミュニケーションに努めて参ります。 ……………………………………………… |