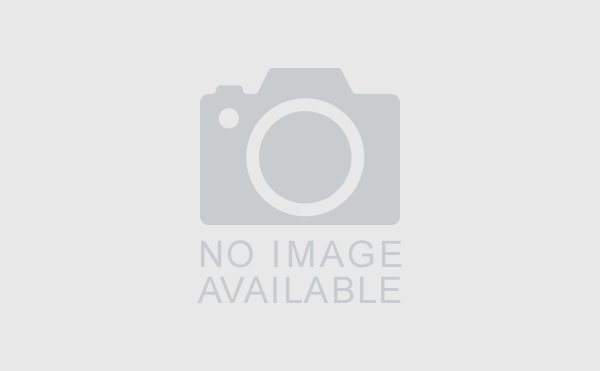食の安全ウォッチNo.84(2025/4/21)
●食品添加物問題で意見書提出・・・・・・・・・・・・・・・2
●情報公開裁判で最高裁弁論・・・・・・・・・・・・・・・・・2
●PFASリスク評価に論文差し替え疑義・・・・・・・・3
●食料・農業・農村基本計画の問題点・・・・・・・・・4
●総会開催のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
●総会記念講演会「農薬の不都合な真実」・・・・10
巻頭言
確実な状況の中でもしっかりと消費者の権利を守ろう
米価が昨年から2倍近く高騰するなど食品の値上がりに私たち消費者は今苦しんでいます。メディアでは健康食品が大々的に宣伝され、消費者をまどわしてもいます。国の対策も効果はみられず、景気回復を多くの人々は実感できていないのではないでしょうか?私たちの将来に対する不安は増すばかりです。
この背景には、3年にも及ぶロシアのウクライナ侵攻をはじめとする世界各地の紛争の拡大により資源の流通が混乱していること、米国トランプ政権がもたらす、関税政策をはじめとする一方的なルールの変更の強制など、貿易ルールや法的仕組みがないがしろにされて、これまでの常識が通用しなくなりそうな状況があるのです。
日米貿易についてみれば、今年3月に米国通商代表部(USTR)が公表した米国議会向け「外国貿易障壁報告書」(NTE)において、日本は非関税障壁が残っているとあげつらっており、今後の日米交渉において、米国側がコメの輸出拡大、小麦の日本側の国家貿易取り扱いの見直し、収穫前及び収穫後の殺菌剤の規制見直し、牛肉のBSE規制見直しなどを取り上げ、日米関税交渉の中で日本側が譲歩してしまうおそれもあります。
国内の消費者政策の中でも、食の分野をめぐっては消費者庁の姿勢が消費者の権利を重視するものとはならず、企業に有利な制度をすすめていることが問題です。
今でも内閣府の食品安全委員会の安全性評価は企業のデータ重視によって消費者が望む予防原則を排除しており、消費者庁・消費者委員会は食品表示のルールを企業が使いやすいものにしています。消費者が求める原料原産地表示では輸入原料がわからない「国内製造」などという表示が横行しており、遺伝子組み換え食品の表示も「分別流通管理済」などと消費者にはわかりにくい表示ルールとなっています。「遺伝子組み換えではない」との良心的生産者の表示も事実上できなくなっており、ゲノム編集された食品も表示は不要とされています。
今後の日本政府の交渉によっては米国の圧力によってこれまで以上に規制緩和が進み、食品安全行政もそれに従ってルーズなものになりかねません。
私たち消費者はこうした事態に対して、状況をしっかりと監視し、行政の対応に注文をつけ、良心的な生産者、流通事業者とともに国内の食料を大切にして安全な食料の流通をはかるよう声をあげていきます。(共同代表 山浦康明)
カテゴリー
ニュースレター