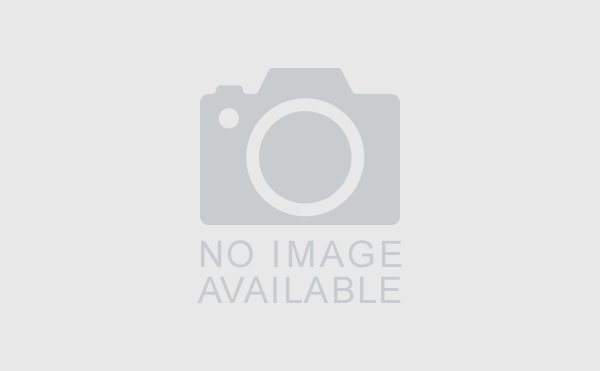参院選に向けた政策についての質問への回答
食の安全・監視市民委員会は、参院選に向けて、各党に食の安全に関する政策を問う質問状を送りました。回答は以下の通りです。投票の参考にしていただければ幸いです。(※空欄は未回答です。回答があり次第、掲載します。)
| 1.米をはじめとした輸入食品の安全性について 米国トランプ政権の追加関税要求に対して、日米交渉が進められています。この交渉において、工業製品の輸出の確保と引き換えに、農畜産物輸入の大幅拡大と食の安全等に関わる基準を非関税障壁として大幅緩和されるのではないかと強く懸念しています。米や牛肉、大豆などの輸入拡大は国内農業への影響だけでなく、輸入時の検査体制が不十分な中で、食の安全を脅かすものです。また、アメリカは収穫後農薬(ポストハーベスト)の規制、農薬残留基準、BSE(牛海綿状脳症=狂牛病)関連輸入条件についても緩和するよう求めています。これらの輸入拡大や規制緩和に対する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | 農林水産品は日米貿易協定ですでに合意しておりこれ以上の譲歩の余地はありません。輸入農産品や食品の安全性は、国民の健康と生活を守るうえで極めて重要な課題であり、いかなる貿易交渉においても、基準が軽視されるべきでないと考えます。 |
| 立憲民主党 | 農林水産物については、日米貿易協定により、既に大部分において市場を開放しています。今般の日米交渉により、更なる市場開放を受け入れた場合、我が国の農林水産業、関連産業及び地域経済に及ぼす影響は甚大なものとなります。したがって、米や牛肉をはじめとする農林水産物は交渉の対象とすべきではないと考えています。 |
| 公明党 | 米国の関税措置に関する日米交渉においては、日本は既に多くの農畜産物を輸入し、米国側が約2兆円の貿易黒字であることから、米国の農業者、食品産業に多大な貢献を行っていることを強く主張していくべきです。加えて、これまでの日米貿易協定の交渉等を通じてできる限りの市場アクセス改善を行っており、拙速な交渉は断じて行うべきではないと考えています。 輸入食品に対する安全性確保については、科学的なリスク評価と国際基準を踏まえて設定された現行基準を踏まえ、適切な検査・監視を実施することが重要であると考えます。 |
| 日本維新の会 | 米の自給率を高めるべく、生産量の 1.5 倍増を目指している。牛肉、大豆などの輸入拡大に際しては、輸入時の検査体制の確実性を求めていく。食料安全保障の観点から、国内農林水産業の保護・育成は重要なテーマであるので、収穫後農薬の規制、農薬残留基準等に関しては、安全性が担保されるべき。 |
| 日本共産党 | トランプ政権の関税要求は、国際ルールに反した不当なもので、毅然として抗議し、撤回を求めるべきです。農畜産物の輸入拡大や食の安全基準の大幅緩和などをトランプ政権への貢ぎ物として差し出す属国的対応は断じて許されません。収穫後の農薬規制、農薬残留基準、BSE関連輸入条件などの緩和に反対です。 |
| 国民民主党 | 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
| 社会民主党 | 米トランプ政権が日本に要求してきているとする、農薬残留基準の緩和、BSE(牛海綿状脳症)関連の輸入条件の緩和について、社民党は、国民の健康と食の安全を守ることが最優先であり、そもそも食品の安全基準を国際的な圧力や通商交渉で緩めることに反対です。 収穫後に使用されるポストハーベスト農薬については、日本では基本的に禁止されており、ポストハーベスト農薬の使用拡大に反対です。食品中の農薬残留基準については、科学的根拠に基づく厳格な基準を維持すべきとしており、輸入自由化や貿易交渉による緩和には反対です。 BSE の発生国からの牛肉輸入に関しても国民の不安が根強く残っていることから、トレーサビリティの徹底や輸入条件の厳格化を求めておりアメリカ側の要請によってリスクを軽視するような輸入規制緩和には明確反対です。 |
| れいわ新選組 | れいわ新選組は、法的拘束力を持つ食料自給率目標を制定し、早急にカロリーベースの自給率を現状の30%台後半から50%に高め、さらに意欲的な目標を追求することを基本政策にしており、自給率の低下を招く輸入拡大に反対します。日本の食料主権を守るためには、国内農業を基盤とした自給体制の強化が不可欠です。収穫後農薬の規制、農薬残留基準、BSE関連輸入条件の緩い輸入農産物の拡大は、国民の健康と国内農家の経営を脅かすため認められません。 |
| NHK党 | ポストハーベスト農薬やBSE等に関するアメリカの主張は、国際的に合意されたコーデックス基準に基づく科学的合理性があり、一概に排除すべきではないと考えます。輸入食品の安全性については、感情的・政治的忖度ではなく、科学的リスク評価と透明な情報公開によって国民の納得を得ることが重要です。過剰なゼロリスク志向ではなく、合理的な規制運用を通じて、国内農業の改革と食の安全を両立させるべきです。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |
| 2.ゲノム編集食品について 新しい遺伝子操作技術であるゲノム編集技術を応用した食品について、食品安全及び環境影響の審査を行なわず、届出も任意とし、表示の義務付けをしないまま、国内市場に出回っています。遺伝子操作食品は、製造過程において遺伝子を傷つけ、想定外の有害作用のリスクを消費者に押し付け、環境にも悪影響をたらすものです。 私たちは、ゲノム編集食品の届け出義務化と安全性評価、環境影響評価の実施、食品や種苗への表示の義務付けを求めています。ゲノム編集食品に対する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | ゲノム編集農林水産物について、その流通等に先立ち、生物多様性の確保の観点から、専門家に意見を伺い、問題がないことを確認した上で、情報提供を受け付け、公表しています。 また、ご指摘の「ゲノム編集技術を応用した食品」について、品質向上等の目的で遺伝子における特定部位をピンポイントで編集したものであり、外来遺伝子が組み込まれてないなど遺伝子組換え食品に該当しない場合は、消費者庁への届出を求めるのみとされております。 一方で安全性について万全を期すため、消費者庁において専門家の意見を聴きながら、編集部位の適切性などについて確認が行われており、遺伝子組換え食品に該当すると判断されたものについては、安全性審査を受けることが義務付けられています。 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集食品・種苗については、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査法の確立が現時点での科学的知見では困難であり、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則の伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。なお、現在市場に流通しているゲノム編集食品については、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいただいている状況と認識しております。 |
| 立憲民主党 | ゲノム編集食品など、論議のある新しい技術を用いた食品等については、予防的見地とともに、消費者が安心して食品を選択することができるようにする観点から、食品表示制度を見直します。 |
| 公明党 | ゲノム編集食品については、政府の遺伝子組換え表示制度に関する検討会の議論を踏まえ、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかの判別がつかず、表示監視における科学的な検証が困難であるなどの課題があることから、現時点では表示の義務付けを行うことは難しいものと承知していますが、表示制度の運用実態、今後の技術進展や社会動向等を踏まえて、情報提供や表示の在り方について、必要な検討を行うべきと考えます。 一方で、国に届出され、市場に流通しているものについては、事業者が、ゲノム編集技術を利用したことについて、積極的に、消費者に対し、情報提供に取り組むべきです。 消費者が正確な情報に基づき正しい選択を行うためには、制度についての理解は不可欠であることから、ゲノム編集食品が作られる過程なども含めて、引き続き国は消費者等への周知・普及に努めていく必要があると考えています。 |
| 日本維新の会 | ゲノム編集食品の生産・流通にあたっては正確な情報を消費者に広く知らせることが望ましい。国民に安心・安全をもたらす情報開示のあり方等を積極的に検討していく必要があると考えている。従来の品種改良技術では、不可能だった低農薬、多収化など難しかったことが、新しい技術を活用することにより、可能となる。食糧問題や環境保全、高齢化や担い手不足といった課題を抱える日本の農業の持続可能性にとってもメリットがあると考える。 |
| 日本共産党 | ゲノム編集技術による農林水産物が開発されていますが、食の安全や生態系への影響など懸念も指摘されています。実用化にあたっては、「予防原則」の立場から遺伝子組み換え食品と同等の規制が必要です。表示についても義務化すべきです。 |
| 国民民主党 | ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
| 社会民主党 | 現状の事業者まかせの「任意届出」では不十分です。すべてのゲノム編集作物・水産物・畜産物について事前の届け出の義務化と公開を法律で定めるべきです。“従来育種と同等”という、政府方針に異議を唱えて追及しています。オフターゲット変異やアレルゲン発現の可能性を踏まえ、食品安全委員会での義務的・事前審査を要求し、国会質疑でも食べ物の安全の観点から食品安全性評価を要求しています。 野外栽培・養殖が生態系に及ぼす影響を予防原則で評価すべきと考えます。外部遺伝子を入れないタイプでも生物多様性への環境影響評価の義務化を提唱しています。 消費者の「選択する権利」を守るため、原材料・種苗レベルでの完全表示とトレーサビリティ制度の法制化を明確に支持します。ゲノム編集技術を含めすべての遺伝子操作食品の原料表示義務化とトレーサビリティ制度確立は急務と考えます。すべてのゲノム編集食品・作物の表示義務(食品・種苗)が必要です。 |
| れいわ新選組 | れいわ新選組は、すべての人が「自分の口に入るものを自分で選ぶ」ことができる社会の実現をめざしています。ゲノム編集食品においても、その安全性に対する科学的な不確実性がある中で、消費者の知る権利・選ぶ権利を守るためには、表示義務は当然、ゲノム編集食品の届け出義務化と安全性評価、環境影響評価を実施ですべきです。特にトレーサビリティや社会的検証を通じて可能な限りの情報開示を進め、意図しない摂取が生じない制度設計を行う必要があります。 |
| NHK党 | NHK党は、ゲノム編集技術そのものを一律に否定する立場ではありません。国際的にも従来の品種改良と同等の安全性が認められており、日本においても健康被害は確認されていません。現在の制度は、科学的合理性に基づくものであり、過剰な規制は技術の健全な発展を妨げるおそれがあります。一方で、消費者の理解を深めるための情報提供体制の充実や、届出情報の分かりやすい開示は今後も必要です。科学に基づいた制度を維持しつつ、過度な不安をあおらない、理性的な対応が求められます。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |
| 3.有機フッ素化合物(PFAS)について 有機フッ素化合物(PFAS)をめぐり、各地で地下水や水道水汚染が起き、住民の健康影響が出てくる可能性があるなど深刻な社会問題になっています。PFASは水だけでなく、食品や身近な家庭用品、工業用品など広く使われており、将来の汚染拡大が懸念されます。欧米では、厳しい基準が設けられていますが、日本ではようやく水道水で基準値を設定しただけです。 私たちは、PFASに対する規制の強化を求め、水道水の水質基準強化、食品の基準の策定、汚染源の解明・浄化措置の実施、汚染地域住民の血液検査と健康影響調査の実施などを求めています。PFASの規制に対する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | 水源から蛇口までの一体的なリスク管理を行い、安心・安全を確保するため、PFAS のうち、PFOS 及び PFOA の水道水質基準(合算50ng/L)を2026年4月から適用します。あわせて、除去・分解技術の実証、水源対策、健康影響に関する科学的知見の充実、国民への丁寧な情報提供や水道事業体への支援を推進します。 |
| 立憲民主党 | PFAS汚染問題は、生きる上で基本となる安全な水の確保の問題です。国民の健康と安全を守る立場として、汚染源特定のためにモニタリングの強化を図るとともに、広く血液検査を行い、PFASの血中濃度が高い場合に相談や支援につながる仕組みを設け、これ以上のPFAS汚染の拡大防止と市民の不安の解消を目指します。 PFASは多くの製品等に使用されてきたことから、関係する省庁が多く、主導的に取り組む省庁がないことから、省庁間の連絡会議などを設けるとともに、PFAS問題に政府が責任をもって取り組む体制をつくります。 PFAS等、特定の化学物質等による水の汚染が疑われる場合に、地方自治体のみに任せるのではなく、国が汚染源を特定し、環境・健康調査をすることを義務付け、飲み水の安全を確保する等の法整備を目指します。 |
| 公明党 | PFAS対策については、地域の方々の不安の声などを真摯に受け止め、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めるべきと考えます。こうした考え方の下、今般、環境省において、飲み水からの健康リスクを減らすこと、「摂取しないこと」を第一に、水道水のPFOS等について、水質検査・遵守の義務がある水道水質基準に引き上げられたものと承知しています。引き続き、健康影響について、国民の皆様に「正しく知っていただく」ため、様々な調査・研究を通じて、PFASのリスクを明らかにしていくとともに、分かりやすい情報発信に努めていくべきと考えます。 さらに、汚染を「広めない」ため、対策技術に関する知見の収集を強化するとともに、汚染を「作らない・出さない」ために、国際条約を踏まえた製造等の規制やPFOS等を含有する泡消火薬剤の管理の徹底なども進めてまいります。こうした総合的な対策を通じて、国民の皆様のPFASに対する不安に真摯に向き合い、対策を進めてまいります。 |
| 日本維新の会 | 新たな環境中への排出を最大限防ぐことが極めて重要であることから、PFAS を含有する泡消火薬剤等の正確な国内在庫量の把握など、管理の強化が必要と考える。すでに外部に放出されている PFAS についてはモニタリングを強化し、情報公開する。当面は「PFAS に対する総合戦略検討専門家会議」がまとめた「PFAS に関する今後の対応の方向性」に基づく対応が重要である。 |
| 日本共産党 | PFASは体内などへの残留性が高く、国際的にも発がん性などが指摘され、欧米等では厳しい規制が行われています。EUでは1万種類以上あると言われるPFASを包括的に規制する動きがでています。一方、日本の規制は、PFASのうち、ストックホルム条約(POPS条約)で製造・使用が禁止されている3種類のみで対応の遅れが際立っています。これでは国内で確認されている高濃度な汚染でも基準値以下で「安全」と認定されかねません。国際的水準の基準値を早急に定め、予防原則に則りEU並みのPFAS規制を進めます。 PFAS汚染が広がる中、住民の健康不安が広がっています。独自に血液検査を実施する自治体が生まれていますが、政府は血液検査に後ろ向きの姿勢を続けています。希望する市民に対し自治体等が実施する健康調査費用を国が負担し、健康影響の研究を進めます。 PFASを製造、販売、使用している事業者が、少なくとも43都道府県、200超の自治体に所在しています。PFAS等が適正に管理されているか、国の責任で調査を行い、飲用水や農産物、地下水、土壌等の各地の汚染状況と、汚染源特定を行い、「汚染者負担の原則」に則り、原因者に除染などの対策を担わせます。農水産物のPFAS含有調査は対象品目が限られ、流通品の中から無作為選択しています。対象品目を拡充し、収穫地ごとに調査を実施します。 米軍基地、自衛隊基地周辺での地下水、河川・湧水、井戸等で深刻な高濃度汚染が確認されています。国の基地への立ち入り調査は、米軍が行った範囲をなぞったにすぎず、地下水等周辺の環境汚染の究明には程遠いものです。米軍の活動優先ではなく、米軍に対して、本国と同様に基地内のPFAS汚染の調査と公表、対策を行なわせます。地下水、土壌汚染が広がる周辺地域の汚染についても、汚染者責任に基づいて本国と同様に、飲用水をはじめ農水産物からPFASが検出された場合の補償と対策を行わせます。 |
| 国民民主党 | 人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。 |
| 社会民主党 | PFAS(有機フッ素化合物)の環境汚染問題に対して厳格な規制と調査の強化を求めています。特に、基地周辺の土壌調査(PFAS 汚染の調査)の実施・強化や住民の健康被害の防止が非常に重要であると考えています。 米軍基地だけでなく、自衛隊基地や米軍基地周辺の土壌・水質調査を早急に実施すべきです。そして、調査の結果、暫定目標値を超える PFAS が検出された地域では、汚染源の特定と除染を進めるべきと訴えています。住民の健康被害防止のため、井戸水を利用する住民への健康診断や血液検査の実施を求める。汚染地域の住民に対する財政援助を拡充し、安全な飲料水の確保を支援することを国に求めていきます。今後の予防措置として国際的な環境基準に沿った規制を導入し、長期的な環境保護を進めていきます。 |
| れいわ新選組 | 「PFOS、PFOAの合計50 ナノグラム」という今年5月8日に中央環境審議会が答申した水質基準の方針は、欧米の基準と比べ、桁違いに高い(注)ので、国民の安全を守るため、より厳格な基準へ変更すべきです。アメリカが事実上のゼロを目指し、EUは個別のPFASではなく、グループとしてPFAS類を使用禁止にするかどうかを検討し、2026年にも結論を出すとしている中、データが蓄積されず、分析・浄化の技術が進んでいない日本では規制が遅れているため、政府は、半導体企業を含む全国的な汚染の調査の実施、汚染地域住民の血液検査と健康影響調査の実施などの必要な対策を早急に講じ、PFASに対する規制を強化すべきです。 |
| NHK党 | PFASのうちPFOAやPFOSは、環境中で分解されにくく、一定の蓄積性・毒性が指摘されており、モニタリングや管理の継続は重要です。ただし、実際には泡消火剤を使用する駐車場などの一般施設も主要な発生源となっており、広く実態を把握したうえで、的確な対策を講じる必要があります。 現時点での健康リスクは限られており、米国CDCなども「高濃度・長期曝露がなければ影響は小さい」としています。今後は、過度な不安を避けつつ、科学的知見に基づいた水質基準や施設管理の見直しを進め、住民の理解と信頼を得られる体制を構築すべきです。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |
| 4.食品添加物の表示について 消費者庁は、2020年に食品添加物の表示の改正を行いました。しかし、表示を拡大・充実させようとの方向はまったくありませんでした。現在の添加物表示は、一括名表示、表示免除や省略などの例外を設定しており、消費者を誤認させる恐れがあります。 私たちは原則に戻り、使用した食品添加物を物質名で、全部表示することを求めています。添加物表示に対する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | 一括名表示、簡略名・類別名の表示については、令和元年度に「添加物表示制度に関する検討会」において、事業者団体、消費者団体、添加物有識者で構成される委員において議論され、文字数の大幅な増加による表示可能面積と見やすさ・分かりやすさのバランスを考慮する必要があることから現状維持とすることが適当と整理されていると承知しております。 |
| 立憲民主党 | 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、加工食品の分かりやすい原料原産地表示の在り方を検討するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換えやゲノム編集食品、アレルギー表示など、消費者が自ら安心・安全を選択できる食品表示制度となるよう見直しを進めます。 |
| 公明党 | 食品添加物の表示については、消費者がその用途について誤認するおそれもあるため、事業者が、個々の物質や目的について、消費者に対し、積極的に情報提供を進めるべきと考えます。 あわせて、食品添加物に係る消費者教育を推進することも重要であり、各種の施策を充実させていきます。 また、消費者の分かりやすさの観点から、栄養強化目的で使用した添加物について、原則全ての加工食品に表示するなど、対策が進んでいると承知しています。引き続き、消費者目線で、表示の在り方について、検討を進めるべきと考えます。 |
| 日本維新の会 | 物質名の表示のみならず、各物質の有用性や安全性、および適切な摂取量等についての知見を広く国民に周知する取組みが欠かせない。食品衛生週間のような食の安全について考える期間を設けて啓発を進めること、義務教育において、給食の時間などを活用した食育の推進の中で、食品添加物に対する正しい知識と理解を深めることが重要である。 |
| 日本共産党 | 食品の表示は、消費者が商品やサービスを正確に知るための権利であり、とりわけ、食品の安全を求める権利、食品の内容を正確に知る権利、食品選択の自由の権利などを実現していく必要があります。食品の安全性が確保されるとともに、消費者に役立つ表示こそ重要だと考えます。 |
| 国民民主党 | 安心・安全な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食 品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー 表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。 |
| 社会民主党 | 消費者の知る権利・選ぶ権利を守るため、すべての添加物の詳細表示を義務付けるべきです。一括名表示(例:pH 調整剤、香料など)ではなく、成分ごとの個別表示を義務付けるべきです。 添加物の使用目的(保存料・甘味料・着色料など)を表示に明記することを求めています。表示だけでなく、食品添加物の使用そのものも、極力少なくし、特に健康影響が懸念される添加物については、使用の禁止や制限も視野に入れるべきとしています。 現行制度で表示義務のない加工助剤やキャリーオーバーも含め、すべての使用添加物を開示する制度への見直しを要求しています。 食品表示基準(食品表示法)そのものの根本的見直しを求めており、消費者庁が事業者寄りにならないように厳しく監視する必要があり、法制度の見直し・消費者庁の機能強化を求めています。 |
| れいわ新選組 | 食品表示制度は、消費者基本法と食品表示法で掲げられた消費者の知る権利を実現し、食品の安全性と消費者の食品選択の機会を確保するための制度であり、消費者の命と健康を守るため、必要で十分な情報が分かりやすく正確に示されるべきです(正確な情報提供)。食の安全と消費者保護のためには、食品添加物と農薬の規制強化は必要です。食品添加物に関しては、一括名表示、表示免除・省略などの例外を廃止し、物質名で全面表示すべきです。 |
| NHK党 | 食品添加物の安全性は既に評価されており、一律に物質名で全て表示することは、消費者の混乱や過剰な不安を招く可能性があります。選択の自由を尊重する観点からも、まずは希望する人が情報にアクセスできる仕組みを拡充すべきであり、全面的な義務化は慎重であるべきと考えます。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |
| 5.加工食品の原料原産地表示について 加工食品の原料原産地表示をめぐっては、例えば食パンでは「小麦粉(国内製造)」と表示され、輸入原材料を使用していても(国内製造)と記載することによって国産原材料使用だと誤認を招いています。また、3か国以上の国から原材料を輸入した場合、「大豆(輸入)」と大括り表示がされています。加工食品のこうした表示を改善し、生鮮原材料に遡って原産地表示をするべきです。加工食品の原料原産地表示に関する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | 加工食品の原料原産地表示制度は、輸入品を除く全ての加工食品を対象としたものであり、消費者への情報提供の観点に加えて、事業者の実行可能性も勘案し制度化されたと承知しております。なお、本制度は、原料原産地表示の対象となる重量割合上位 1 位の原材料が加工食品の場合、原産地として製造された地名を表示することを基本としており、その趣旨は、原材料となった加工食品の製造に使用されている原材料の調達先が変わることや、当該加工食品の生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものです。 他方、原材料が加工食品である場合であっても、客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産地まで遡って表示することは可能となっております。 引き続き、消費者の誤認を招かないよう、制度の普及・啓発を行っていくことが重要と考えています。 |
| 立憲民主党 | 2,4の回答に重なりますが、消費者が選択する権利を十分に確保できる表示制度を目指すべきであると考えます。 |
| 公明党 | 加工食品の原料原産地表示制度については、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合であっても、原材料のうち、最も重量割合が大きい生鮮原材料の原産地が確認できる場合には、製造地表示に代えて、その生鮮原材料の原産国の表示を可能としています。 こうした仕組みを通じて、事業者が、消費者に対し、分かりやすく信頼できる情報を提供することが重要です。 一方で、原料調達先の切り替えに伴う事業者の実務負担にも配慮する必要があります。消費者・事業者双方の状況等を勘案しつつ、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じて、制度の在り方について検討を進めることが重要であると考えます。 |
| 日本維新の会 | 適切に消費者が商品を選択できる要素として、原料原産地表示は大切である。このことは、BSE 問題(牛海綿状脳症)や食品偽装事件などを受けて、本制度が設けられた経緯からも明らかである。一方で、加工食品を製造する中小企業等が適切な原産地表示をできるように環境づくりや技術開発を行政が支援すべきである。 |
| 日本共産党 | 加工食品の原料原産地表示について必要です。 |
| 国民民主党 | 安心・安全な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食 品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー 表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。 |
| 社会民主党 | すべての加工食品に対して、「主な原材料」の原産国名表示を義務付けるべきであり、曖昧な表示や例外規定は廃止・見直すべきです。 ご指摘のような「輸入品→国産」のような紛らわしい表記は是正を「製造地=日本」だけで国産と誤解させるような表示に対しては「主原料の産地」を明確に記載するルールを提唱しています。「国産または輸入」「複数の国がある場合は最も多いもの」などの包括的・あいまいな表現についても、より正確で厳格な表示に改めるべきであると指摘してきています。特に輸入原料への不安(農薬・添加物・遺伝子操作など)を背景に、原産地表示が購買判断の重要基準になると認識しています。 表示は単なる情報提供ではなく、消費者の「知る権利」「選ぶ権利」を保障されることが重視であると考えます。表示義務の対象外(例外措置)となっている複雑な加工食品、外食・中食などについても段階的に表示義務を拡大すべきと提唱し、加えて、供給ルートのトレーサビリティ確保(履歴追跡可能な仕組み)も法制度で強化すべきとしています。 |
| れいわ新選組 | 加工食品の原料原産地制度は、本来、消費者が国産か外国産かを判別することを可能とし、食料自給率向上に資するものです。しかし、「小麦粉(国内製造)」という表示は、実際には輸入小麦を国内で製粉したものであるにも関わらず、多くの消費者に誤認を与えています。これは、食品表示制度の根幹である「正確な情報提供」に反します。れいわ新選組は、真に消費者の立場に立ち、生産地が明示される制度への改正を求めます。 |
| NHK党 | 加工食品において、生鮮原材料まで遡ってすべての原産地を表示することは、実務上極めて困難です。輸入原料の混合や加工工程の複雑さを考慮すれば、主要原材料に絞って現実的な範囲で対応しつつ、詳細を知りたい消費者には補完的な情報提供手段を整備すべきと考えます。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |
| 6.「機能性表示食品」をはじめとした健康食品問題について 昨年の小林製薬の機能性表示食品「紅麹サプリ」による重大な事故にみられるように、機能性表示食品は、機能も安全性も事業者任せの不安定な制度です。事故の届け出制度を作るなどの弥縫的制度改革では不十分です。私たちは、当初から機能性表示食品制度に反対してきましたが、改めて制度の廃止を求めます。また、インターネットCMを含む「健康食品」の宣伝・広告の規制を強化すべきであると考えています。機能性表示食品を含む「健康食品」に対する見解を伺います。 | |
| 自由民主党 | インターネット CM を含む「健康食品」の宣伝・広告も含め、法令上問題となるおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処していくものと承知しております。 機能性表示食品制度については、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」で取りまとめた対応方針において、①健康被害情報の提供義務化や②錠剤・カプセル剤等食品への GMP の要件化、③表示方法の見直し等、本制度の信頼性を高めるための措置が整理され、この方針を踏まえて、令和6年8月に食品表示基準を改正されたと承知しております。 このうち、GMP の要件化については、製造等施設における GMP 遵守が円滑に進められるよう、消費者庁の専門チームが、各製造等施設に対し、製造管理・品質管理等の GMP 実施状況の確認・助言を行っているところであると承知しております。 今般の改正により本制度の信頼性が確保されるよう、制度が適切に運用される必要があると考えております。 |
| 立憲民主党 | 小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントの摂取による死亡事例や入院事例等の深刻な健康被害の発生を受け、健康被害への早急な対応と、原因が特定できていなくても速やかに報告することを義務付ける法改正や、原材料の受入れを含めた製造管理基準(GMP)の認証取得の義務化などを実現します。 サプリメントのように濃縮した成分を定期的に摂取する医薬品に限りなく近い食品については、十分な安全対策や、被害者の救済機関の設置等の具体策を検討します。 特定保健用食品や機能性表示食品をはじめとする、いわゆる「健康食品」については、消費者による商品の有効性や安全性についての誤認や過信が起こらないよう、科学的根拠に基づく情報公開、表示・広告の適正化等について、消費者委員会専門調査会の議論を踏まえ、制度全体の一体的な見直しを進めます。併せて、不適切な表示の取締りを一層強化します。 |
| 公明党 | 「紅麹サプリ」の問題は、機能性表示食品を信頼して購入した国民の皆様の思いを裏切るものであり、絶対にあってはなりません。 まずは、国民の命と健康を守るため、消費者や被害者等に寄り添った対応を着実に推進するとともに、新規成分に係る安全性等をより慎重に確認する仕組みや事業者が情報提供を怠った場合の営業停止処分など、再発防止策を徹底して実施すべきと考えます。 その上で、必要に応じて、本件及び同一の事案の発生を防止するための食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種・営業許可施設の基準の在り方などについて、検討を進める必要があると考えます。 |
| 日本維新の会 | 「紅麹」問題のさらなる因果関係の究明と報告義務の強化、被害者救済の充実を求めていく。機能性表示食品は食品であるにも関わらず、消費者は薬品の効能に似た機能を求めて購入する傾向もあること等から、政府の責任で適切な情報を消費者に届ける必要があると考える。 |
| 日本共産党 | 「機能能性表示食品」制度は、事業者が機能性の根拠を添えて消費者庁に届け出れば、機能性を表示して販売できる制度です。「紅麹問題」は安全性評価を企業任せにしたために大規模な健康被害が生じて初めて政府が対応することになった大事件です。届出制ですまされることから、食品の安全性についても、摂取による事故が起こった場合も、国が安全性を確保する措置や担保がきわめて不十分だということです。この「機能性表示食品」制度は廃止することが必要ではないかと考えます。 健康被害をすぐ国に報告、サプリメントを加工する工場の「適正製造規範=GMP」管理など見直しがありましたが、不十分です。 「特定保健用食品」でも誤解を生む広告もあり、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品の区別は消費者には判断が難しいものです。いわゆる健康食品の安全性、効果については客観的検証制度が必要です。 |
| 国民民主党 | 機能性表示食品による健康被害について迅速な原因究明を行います。機能性表示食品における審査制度を見直し、安全性の確保を進めます。 |
| 社会民主党 | 機能性表示食品制度は、事業者の“自己責任”に基づく表示制度であり、信頼性や安全性に重大な懸念があり、消費者保護と科学的根拠の確保を最優先とするように現行制度の見直しと厳格化を求めています。機能性表示食品は「企業の責任で科学的根拠を提出すれば、国の審査なしで機能性表示ができる」制度(2015 年施行)であり、「消費者に誤解を与えるおそれがあり、機能性や安全性の裏付けは国が責任を持って確認すべきと指摘しています。 |
| れいわ新選組 | 「機能性表示食品」については、かねてより貴委員会をはじめ多くの市民団体から安全性等に関する様々な懸念が出されていたにも関わらず、今般の紅麹サプリ事件が発生してしまいました。国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出さえすれば、機能性を表示することができる機能性表示食品制度は、政府が機能性と安全性を確認せず、事業者任せで国民の安全が担保されていないことが紅麹サプリ事件によって明白になったため、廃止すべきです。 |
| NHK党 | 機能性表示食品は国の審査を受けずに販売できるため、根拠の質にばらつきがあり、消費者に誤解や不安を与えるおそれがあります。問題発生時の対応や情報公開の強化など、制度の信頼性を高める見直しが必要と考えます。 |
| 参政党 | |
| 日本保守党 | |